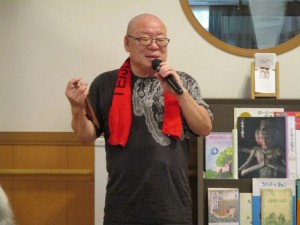朝靄が凄かったです
いつものように朝5時過ぎにベットを抜け出し廊下から外を見ると凄い勢いで靄が空に向かって上って行くのを見て、「今日も暑くなるな」と思い、朝のウォーキングマシーンでの歩きとお経を終えてゆったりと湯船に浸かり朝食を頂いた後、再び廊下の窓から外を見ると「めっちゃ暑そう」と言う事で本日も本部施設で仕事をしてます。と言うより、14時から杉和会の緊急理事会があり、議題が銀行への追加融資がメインなので、正直朝からストレス一杯です。と言うのも、盲養護老人ホーム優・悠・邑 和(なごみ)は措置施設である為に市町村の判断に委ねられる部分が多く、市町村による考え方に大きな違いがある現実を今は痛切に感じでいます。私は自分で言うのも何ですが岐阜県の中においても、全国の中においても多くのネットワークがあるので、措置制度の問題点を1つ1つ紐解いて、厳しい状況に置かれている方がより豊かな生活が出来るためにも頑張っていかなければと考えています。14時からの理事会では融資に対する理解は得られましたが、多くの方が入居して頂く為のアプローチにより努めるようにと理事・監事の皆さんから叱咤激励されたように感じました。今は『熱い思い』だけではクリア出来ない現実を理解した上でより一層努力していかなければと考えています。理事会が終了してから若干の打ち合わせをして、16時からは人材紹介の社長との打ち合わせです。当法人の外国人材の活用はEPAによるインドネシア人と特定技能で介護をクリアしたベトナム人とネパール人ですがどの職員も一生懸命に働いていてくれます。もちろん、彼らが生活しやすいように、仕事がしやすいような環境を作っていかなければ次々と繋がっていかないので、それなりにハード面やソフト面への配慮をしていかなければいけないし、その為にはある程度の資本投資もしていかなければいけないと理事長として考えています。介護の人材不足が始まったのは平成18年からだと思っているのですが、これからはますますこの状況は深刻になると考えています。嘆いていても問題解決しないので、先をみた展開をしていかないといけないので、色んな手立てを講じていかなければとも思っています。人材は確保して育てていかなければいけないので職員教育も是は是、非は非でしっかりと取り組んでいかなければと思っています。お陰さまで本部施設の正職員の平均勤務年数は10年を越えました。この現象はありがたい事だと考えているのですがリピーターの皆さんはどう思われますか。まさか、人件費が高くなって大変だ等と思われてませんよね。