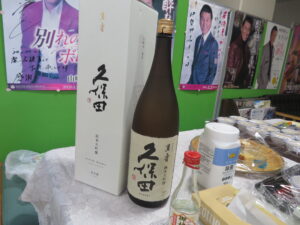週刊現代の記事から
令和7年1月7日
大見出しが『時代遅れな「減反政策」の代償。「コメが食えない日本人」が激増する』を興味を持って読ませて頂きました。
昨年のコメ不足は、本当に切実なものがあったと聞いています。「聞いています」と他人事の様に言ったのは、当法人の本部と和合の施設は、本部施設の地元農家さんと契約をして提供して頂き、盲養護老人ホーム優・悠・邑 和(なごみ)は、所在地である垂井町の農家さんから提供して頂いていて、年間を通したコメの確保をして頂いているからです。コメ不足の話が頻繁に出ていた頃、地元で多くの田圃を頼まれて作られている方から聞いた話として、「減反政策は廃止されたと聞いていたのに、一部を休耕にしてくれと地元の方から言われたので、納得がいかずに作付けをしようとしていたら、農協の職員が我が家に来て何とか休耕に協力してくれと言われ、納得はいかなかったが結果的に休耕にした田圃がある。」と言われたので、私自身何が何だかわからなかったのを思い出しました。
8月にコメがスーパーの棚から消えた時には「9月に新米が入荷されるので、しばらく待てば大丈夫」的な話が流れてきましたが、よくよく考えてみたら、いつもより早くに流通したコメを購入していて、今年の天候によっては昨年以上の深刻なコメ不足になってしまう可能性があると言う事で、本来であれば政府であったり、農林水産省が何らかの政策をしなければいけないと思うのですが、何ら政策変更はされていないと理解しています。
今回の記事を書かれた山下一仁氏(キャノングローバル戦略研究所研究主幹)によれば、【安倍晋三元首相は2018年から「減反政策を廃止する」と主張しましたが、これはまやかしです。確かに国は農家に対する「生産数量目標」の通知はやめました。ところが、飼料用米や麦などへの転作補助金はむしろ拡充したのです。さらに農水省は毎年、翌年作るコメの「適正生産量」を決定・公表し、これに基づいてJA(農業協同組合)などが農家にコメの生産を指導しています。要は、実質的な生産調整が行われており、実態は全く変わっていないため、コメの生産量が右肩下がりになっているのです。】との内容を見て、私は「日本のお米は世界の中で最も安全で美味しい」と思っているので、作りたい農家さんに作りたいだけ作って貰い、生産過剰なものについては輸出をしていく政策をとるべきではないかと思っています。こんな単純な事では無いのでしょうが「出来る事から手を打つ」事こそ肝要だと考えています。リピーターの皆さんのご意見をお聞かせ下さい。